
|
|
音円盤アーカイブス(1月2月) 2年前の春先、倉敷の「レコード屋」で買ったもの。 LOLA!というレーベルが珍しかったし、ペリコ・サンビートのリーダーアルバムは持っていなかったので、どれどれという感じで買ってみた。 今、クレジットを見るとピアノにはBERNARDO SASSETTIが参加している。 この人のそこはかとない寂寥感につつまれた水晶の輝きのような叙情的なピアノの音を聴いていると心がいつのまにか穏やかになる。 一方PERICO SAMBEATのサックスはいつにましてフルトーンで鳴っていてケニー・ギャレットか?と思わせる場面もある。 2曲目「DE CAMINO」でそれが覗える。 手拍子、パーカッションが入った賑やかなリズムの中をペリコのアルトがエネルギッシュに駆け巡る。続くサセッティのピアノはいたってマイペース、自分の持ち味を崩さない。 動のペリコ、静のサセッティ、両者の対比が面白いトラック。 6曲目はサセッティの冬の雲の谷間から差し込む日に光の様なピアノの旋律に続いてペリコ・サンビートもコルトレーンの「セイ・イット」のような優しく厳かな吹奏を披露。 この奏者の力量が覗えるトラック。 ラスト「LO PILLAS?」はややフリーな導入部からラテンの血が煮えたぎる情熱的な演奏。 スペインの代表的なアルト奏者のラテン性がよく分かる近況盤。 録音は2000年2月14,15,16,17日 バレンシア --------  2002年の暮れにDUから買ったCD。 TONE OF A PITCHというポルトガルのレーベルからのもの。 ポルトガルのジャズシーンは情報もあまりこちらにはいってこないので馴染みが薄いのであるが、JAZZPORTUGAL.NETというサイトもつくられているほど、それなりのジャズシーンが確立されているようだ。とは言っても首都リスボンの人口がわずか100万人だそうだからそれなりの規模だと推測されるが、このレーベルからも何人か新人の作品がリリースされていて注目にあたいする。 ポルトガルのミュージシャンが77名紹介されているが、名前をざっとみたところ、CARLOS BARRETTOやBERNARDO SASSETTIくらいでほとんど聞いたことのない名前。ペリコ・サンビートやアルバート・サンズなどスペイン出身の名前もはいっていたが・・・ このCDにはTPにAVISHAI COHENの名前がクレジットされている。 もっとも購入した当時は今ほど騒がれてなかったし、実際プレイのほうもFSNTのトリオ盤ほど弾けた演奏は聴けないのであるが、非凡な才能の断片は聴き取れると思う。 テナーサックスのJESUS SANTANDREUのほうがどちらかというと目立ったプレイをしており、一言で言うとマイケル・ブレッカーしているのだ。 1曲目の一糸乱れぬ複雑なラインのアンサンブルなど迫力もあるし、情熱を感じさせる楽曲の出来映えに感心させられる。 リーダーのNELSON CASCAISが2曲を除いて作曲を担当しており、4曲目の「THERE`S A STAIN ON MY SHIRT」など60年代のウェイン・ショーター風だし、アップテンポの6曲目「LOOKING BACK」もミュージシャンうけしそうないい曲だと思う。 ラストの「SEI LA!」ではテナーとトランペットが同時にアドリブを繰りひろげスリルに富んだジャズを展開している。 録音は2001年5月20,21日 ポルトガル ポルトガルのジャズも無視するわけにはいかないねぇ! -------- 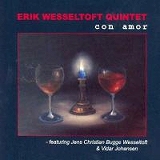 先週DUから届いたばかりのCD。 ノルウェーのギタリストのリーダー作でオーソドックスな音つくりなことが通販のページに書かれていたので、どんなもんかなぁ?と注文してみた。キーボードにブッゲ・ウェセルトフトが参加しているのも気になった。 今日も部屋の外は木枯しが吹いて寒そうだ。 こういう休みの日はぬくぬくとしたこのパソコンの置いている部屋で過ごすのが正解か? すこし濃い目に淹れたコーヒーにこの前買ったBAILEY`Sのクリームリキュールをいれてマッタリと休日の昼下がりを過ごしています。 そんな感じに聴くのにピッタリとはまった一枚といっていのかなぁ・・・ ゆったりとしたメロディアスな曲が多く、ギターやオルガンのソロもしゃかりきになってソロをとるのではなく、常に余力を残し全体のバランスを眺めつつ余裕のプレイ。 この少し緩めなプレイがなんとも心地よい。 決して手抜きしているわけではない。 曲ごとの解説はやめよう。 BUGGE WESSELTOFTがピアノで参加していることも、サウンドメイキングの一任を担ってはいるが、必然性があるとは言えない。 そんな事より、ERIK WESSELTOFTの新曲をセッションに集まったミュージシャンが楽しんで演奏している様が窺えて聴いているこちら方にもその雰囲気が伝わってくる。 個人的には、ERIKのオクターブ奏法によるメロディが印象的な4曲目「MOUNTAINJAZZ」、以前紹介したアル・ガーファのPABLO盤に雰囲気がそっくりなマイナー調の6曲目、「THE WHICHES DANCE」ボッサリズムの8曲目「HAMBROS PLASS」が気に入っている。 サウンド全体の印象はマイルド、クリ-ミー、スムージィー。 録音はオスロ RAINBOW STUDIO 箸休め的にこれからよく聴きそうな一枚。 --------  1996年DDQからリリースされたもので2003年シャレオ地下でおこなわれていた中古市でGETしたもの。LPコーナーの倒産流れ品だったみたいで例の国旗のシールが貼り付けてあった。 値段は別にして珍しいレコード、CDが入荷する店だっただけに今考えてもなくなってしまった事が残念だ。 この時はそんな訳で結構珍しいブツを買い込んだ。 このCDもジャケットは知っていたが現物は初めて見たので嬉々として買った次第。 アントニオ・ファラオの初リーダー作品で、さすがに力がはいっている作り。 1曲目から怒涛の勢いでカルテット全員がゴール向かって一直線という感じ。テナーのBOB BONISOLOは以前のスティーブ・グロスマンを彷彿させるマナーでテナーを吹きまくるわ、ファラオはファラオでタテノリ、ヨコノリ縦横無尽にラインを弾きまくり音楽を推進させていく。ジャズへの情熱とスリルを感じさせるトラックで、この1曲目から演奏に引き込まれていくのである。 2曲目はややスローダウンしてミディアムテンポの曲。 ファラオのソロがハンコックの手法を使いながらも新鮮なところを感じさせ非凡なピアニストであるのがよく分かる。 3曲目が一番気に入っているトラック。 この感じ昔TIMELESSからでたマイク・ノック~マイケル・ブレッカー・カルテットを彷彿させる。 複雑なラインを熟練したテクニックで猛スピードで疾走するカーレースを見ているかの様なカルテットの動きに彼らの高い音楽性の一部が垣間見れる。 4曲目の「NAIMA」と9曲目「GIANT STEPS」コルトレーンがらみの曲は、トランペットのFRANCO AMBROSETTIがテナーのBONISOLOに代わる。アンブロゼッティには悪いがここは、テナーカルテットでいって欲しかった。 5曲目は「IN A SENTIMENTAL MOOD」。 こういう曲弾いてもファラオはさすがにうまいねぇ! 全9曲。録音は1996年3月27,28日 ミラノ --------  ジョン・エリスってFSNTからリーダー盤だしている同姓同名のテナー奏者もいるが、このジョンはトランペット奏者。 これも昨日のアントニオ・ファラオ盤と同時に購入した。 サイドメンで買った。 FEATURING: MICHAEL BRECKER,AL FOSTER,EDDIE GOMEZ,CHRIS POTTER,EDWARD SIMONなのである。 これで即購入が決定。 マイケル・ブレッカーは1,2曲目に参加。残りの曲はクリス・ポッターがテナーを担当している。 マイケルは実に伸び伸びしたプレイをしている。 最近のリーダーアルバム完成度は高いし、サウンド指向の高い音楽性が素晴らしいとは思うのですが、反面以前のような自由度の高い時によってはぶち切れたような(マイケルの場合、それも計算済みのプレイかもしれないが)怒涛のインプロビゼーションが少し薄められた気がするのは私だけだろうか? ソロイストとして現存のテナー奏者のなかでベスト3に個人的には確実にはいる彼のプレイをもっともっと聴きたいと思う。 このような自費出版にちかいアルバムに参加できるのであれば、もっと様々なセッションにこの素晴らしいテナー奏者を起用すべきだろう。 クリス・ポッターはマイケルとは反対に自己のリーダーアルバムで最もその真価を発揮するミュージシャンだとは言えないか? ジョー・ロバーノからポール・モチアン経由で体得したサウンド指向の音楽性が自身のオリジナル作品、自分で選んだフォーマット、ミュージシャンの中でその演奏も最高に映えると思う。 そういう点でマイケル・ブレッカーというミュージシャンはクリス・ポッターはじめマーク・ターナーやクリス・チークら若手テナー奏者に比べて昔かたぎと言ってはなんだが、アドリブ指向プレイ指向の高いミュージシャン なのだと思う次第。 エディー・ゴメスとアル・フォスターのコンビは良好である。 リーダーの夢がかなったレコーディングとなったことは喜ばしいのであるが、肝心のリーダーの存在感が残念ながら一番乏しいのはこのメンバーだから仕方ないか? 作曲も可も不可もないといったところで、これならば他のジャズオリジナルやスタンダードを数曲加えた方がアルバムとしてのバラエティーは富んだ作品になったんではないだろうか? なにはともあれ有名ミュージシャンの参加した珍しいアルバム。 --------  NISSE SANDSTROMの名前が懐かしくて1994年に岡山のLPコーナーで買ったCD。 ロシア出身のテナー奏者SLAVA PREOBRAZHENSKIとのツーテナー共演盤。競演ではなくて心暖まる会話が続く共演盤。 1曲目はSANDSTROMのマイナーブルース「RUSSIAN BLUE」で幕を開ける。SLAVA PREOBRAHENSKI,ピアノのHORACE PARLAN,NISSE SANDSTROM、ベースのSTURE NORDINとソロが続く。 50年代のハードバップタッチの哀愁味を帯びた実にいい曲。 2曲目はジュニア・マンスの有名な「JUBILATION」。 テナーはSLAVA, SANNDSTROMの順。二人のテナースタイルはレスター・ヤングからフォーブラザーズの白人テナーの系譜、伝統を引き継ぐ正統スタイルだが音色はSANDSTROMのほうが、ソフトでマイルドな口当たり。 ミディアムで演奏される「FOR ALL WE KNOW」に続きこれも懐かしい「BEWICHED」。SLAVAのソロバラード。 5曲目はタッド・ダメロンの「OUR DELIGHT」。ここではホレス・パーランがノリの良いソロを披露。SLAVA,SANDSTROMと快調なソロが続く。 6曲目もトミフラの有名な「MINOR MISHAP」。トミー・フラナガンというとその後継者として日本に寺井尚之という自身もライブハウスを大阪で経営するピアニストがいるが、一度ライブを観てみたいものだ。トミー・フラナガンは一度広島のジャズフェスティバルで観ている。手抜きのない、むしろレコードで聴く落ち着いた印象よりハードにバッピッシュに速いフレーズを弾きまくる姿にレコードだけじゃ分からないなぁという感を抱いた事を覚えている。 ガーシュインの「HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON」。 映画「ラウンド・ミッドナイト」で女性歌手が唄う場面があってデクスターの伴奏とともに強烈な印象に残ってこの曲を覚えた。 渋くていい曲だと思う。この曲はSANDSTROMのソロバラード。 残り3曲はラストまで快活な明るい曲調の作品がツーテナーで演奏され楽しく締めくくられる。 北欧のベテランテナーの近作(といっても10年以上前だが)はモダンジャズの名曲を演じた楽しい作品になったと思う。 録音は1993年7月4日 --------  今考えてみるとちょうど10年前の1995年から1996年にかけてジャズ熱が最も薄れていた時期だったと思う。 前年94年に急性肝炎を患ってそれまでの生活を見直そうと、体を鍛え直したのが翌年95年の夏、フィットネスクラブに入会したのだ。 ウォーミングアップで20分自転車漕ぎ、それからトレッドミルにのって8km走った。少し休憩をとって筋トレ、ストレッチと週4日は4時間近くジムで過ごした。それ以外の日は外を走ってダンベルとチューブトレーニング。出張にも持っていった。 食事にも気をつけた。和食中心で高タンパク、高ビタミン、低脂肪の食事を心掛けた。サプリメントにも凝って、トレーニングの雑誌にも目をとおす。 約2ヶ月で5kg減量、ストイックな生活ながらゲーム感覚、実験感覚でこうしたら自分の体がどう変化していくか?という感じで楽しみながら今考えるとやっていたような気がする。 当然体は軽くなり、元気になった。高校生の頃の体力に戻ったような気がした。半年くらいたってから酒も再び飲みだした。 体が元気だと酒も自然と強くなり、うまいしその頃からワインに凝りだして料理とのバランスにも気を配りだした。 トレーニングも続けていたし、ワインが新しい趣味みたいになりだして、ジャズも聴き続けていたけど以前程、その頃は熱心ではなくなりつつあった。輸入盤の購入が減ったし、スイングジャーナルも買わない月が何回かあった。 それでも毎月何枚かのCDを買って、毎日何かジャズを聴いていた。 そんな時にこのCORNELIUS CLAUDIO KREUSCHのCDを倉敷のGREEN HOUSEで見つけたのだ。冴えないジャケットだがケニ-・ギャレットやマーヴィン・スミッティ・スミスなどのメンバーに関心をもって買ったのだ。リーダーの名前は全然知らなかった。 こんなに激しいプレイをするケニ-・ギャレットのプレイが録音されたCDはあまり他にないのではなかろうか? とにかく吹きまくる。吹きまくる。 ドイツ構造主義(かってにイメージした言葉)的なかっちりとアレンジされたポキポキと折れそうな硬い感じのテーマを経て縦横無尽に暴れまくるケニ-のアルトソロを筋トレしながらよく聴いたものだ。ダンベルのあがる回数がこれを聴くと1,2回増えたもんである。 今はあまりトレーニングもしていなくて週に1回近所の公園を5kmくらい走るだけで、すっかり太ってしまった。 その分ジャズ聴けるからいいか? i-pod買って聴きながらトレーニングするのが両立して一番よいかなぁ? --------  昨日アマゾンから届いたばかりのCD。 シーマス・ブレイクとビル・スチュアートが入っているので注文した。早速聴いてみる。 一曲目「METAPHORICALLY SPEAKING」は彼MANUEL VALERAがニューヨークに出てきた2000年の冬に作曲したこのCDでは最も昔の作品らしい。二つの異なったテンポが交錯するユニークなメロディを持つ楽曲で、シーマス・ブレイクとヴァレラのソロが聴きもの。ビル・ステュアートのドラムはたくみなタイミングではいるスネアドラムやハイハットのビシバシ具合が聴いていて快感である。 ドラムはこのSTEWARTとHORACIO"EL NEGRO"HERNANDEZが仲良く5曲づつ分け合って叩いている。 シーマスが参加しているカルテットの演奏はすべてステュワートが担当。 3曲目「SIMPLICITY」でのシーマス・ブレイクのフラジオを巧みに使ったソロテクニックに耳を奪われる。 続くVALERAのソロも現代ジャズピアノの髄を表現するかのようなアップトゥデイトな演奏。リズムを受け持つJOHN PATITUCCIとBILL STEWARTも鉄壁のバランスでサポートしている。 4曲目はHORACIOとPATITUCCIの定形ビートにヴァレラのピアノソロが自由に泳ぎまわる。5曲目は叙情的なメロディを持つELISEO NEGRETの作品。 6曲目もシーマス・ブレイクのソロが素晴らしい。この人今絶対伸び盛りだと思う。以前に増して楽曲への独自のスタイルによるオリジナリティ溢れる解釈と楽器をコントロールするテクニックが一体化して心・技・体すべてが充実していると思う。9曲目は「SAY IT」。ピアノトリオで厳かに演奏される。 MANUEL VALERAはキューバ出身のこのレコーディング時23歳の若者でラテン音楽(キューバ、プエルトリコの音楽、ブラジル音楽)とコンテンポラリーなジャズのイディオムを融合させて将来を嘱望されているヤングライオンだと実際ビルボードなどで好印象のレビューをされている。 このファーストCDを聴くとその事が納得できると思う。 録音は2003年10月20,22,28,29日 NY AVATOR STUDIO -------- 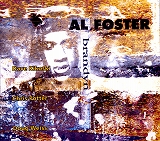 1997年にLAIKAからリリースされたアルバムで、アル・フォスターはもとより、クリス・ポッターやデビッド・キコスキーがサイドメンで入っているのが購入動機だったと思う。 今、アル・フォスターのリーダー作はこれを含めて3枚所有しているが、一枚のアルバムとしてはこれが一番まとまっているのではなかろうか? ファースト作はフュージョンに色眼鏡を使った中途半端な駄作だった。2枚目はエキセントリックなつくりでマイケル・ブレッカーや菊地雅章の力演がおさめられた力作であったが、やや焦点を一枚の作品として絞りきれていないきらいがあったと思う。実際このアルバムは今でもよく聴く。 アル・フォスターの名前を知ったのは一連の70年代マイルスのレコードからだったが、それ以前にBLUE NOTEのブルー・ミッチェル「DOWN WITH IT」などに吹き込みがあるのを、大学時代の行きつけのジャズ喫茶「JOKE」で知り、マイルスのバンドでのプレイが特別なものであり、この人本来はオーソドックスなジャズドラマーなのを知った次第。実際マイルス引退後は、ピアノトリオの録音なんか結構多かったと記憶している。 アル・フォスターの小技のきいた熟練のテクニックはCD時代になってその細かいところがはじめてちゃんと記録されるようになったのではないだろうか? このアルバムではリーダー作ということもあって5曲も自作曲が収録されていてその作品がまた力作、佳作揃いであり、作曲家としても能力を発揮しているといえよう。 そういえば、昔からいい曲を書く人だったことを今思い出した。 クリス・ポッターは現在より素直というかストレートアヘッドに邁進するスタイルでカッコいいアドリブフレーズを極めまくる。 このアルバムに収録された曲はポッターやキコスキーのリーダー盤でも演奏されている曲があるので、聴き比べても面白いかもしれない。 ラストはウェイン・ショーターの「BLACK NILE」で締められる。 録音は1996年10月14日 オランダ STUDIO44 アル・フォスターがサイドメンではいっているとそのアルバムは安心して買うことのできる作品だといえよう。 すくなくともリズムに関しては、一点の曇りもない出来具合だから・・・ --------  初めてジャッキー・ペルツァーを聴いたのは、ルネ・トーマのレコードだった。結構鋭角的というかヨーロッパのアルティストにしてはエッジのある音使いで吹くなぁという印象を持っていた。 このCDは六本木WAVEの広告で知って1994年の今頃入手した。 メンバーはJACQUES PELZER(SAX,FL)PHILIP CATHERINE(G) PHILIPPE AERTS(B)BRUNO CASTELLUCCI(DS) 中堅、ベテラン勢でかためられたグループサウンドは極めて洗練された響きで気品さえ感じられる。最も楽曲のもつ雰囲気は彼らヨーロッパの土壌に成り立ったジャズに巧みにその50年代ジャズ(黄金時代)が持っていた輝きをトランスレートしているのだ。決して宮廷音楽でもなんでもなく正真正銘、真正面のジャズだ。 取り上げられているジャズオリジナルが最高に良い。 TADD DAMERONで「GNID」「SOUL TRANE」 HORACE SILVERで「LOVE VIBRATION」 GIGI GRYCEで「SALUTE TO THE BAND BOX」「QUICKSTEP」「CONSULTATION」「SOCIAL CALL」「DELTITNU」「MINORITY」 その他は「THEME FOR ERNIE」「I DIDN‘T KNOW WHAT TIME IT WAS」「SPEAK LOW」 タッド・ダメロンは作曲家として素晴らしい才能の持ち主なのは、認知していたけれども、このCDを聴いてジジ・グライスもそれに劣らぬ作曲家であることを知った。 一聴さりげなさを感じる楽曲が何度か聴いているとその楽曲のもつ深さ、豊かさが次第に理解できてくるスルメ曲をたくさん発表しているミュージシャンだと思う。 ラストは「MINORITY」。 このアルバムのリーダー、PELZERもTADD DAMERONもGIGI GRYCEもジャズ界においてMAJORITYにはなれなかったが、マイナーにはマイナーとしての輝きを放ち続けた、ミュージシャンズミュージシャンだと思う。 録音は1993年6月ベルギー、ブリュッセル IGLOO STUDIO --------  1997年に東京出張で行った折、新宿ディスクユニオンの中古売り場で買ったもの。探していたのが、1Fでは見つからなかったので発見した時は少し嬉しかったのを覚えている。 もとはと言うとデイブ・リーブマンのクレジットがあったので買い物リストに入れていたのだが、そのリーブマンは1,5曲目しか参加していない。1996年のコンラッド・ハーウィッグ盤(DOUBULE-TIME)にリーブマンが参加したCDも出来がよかったのでこのアルバムも同じように期待していたのだ。 あとの曲はリッチ-・ペリーが参加している。 あんまりこのサックス奏者に感心した覚えがないので少し不安を覚えるが聴いている内にそれは杞憂に終ったことを直ぐに悟る。 1曲目マルグリュー・ミラー作曲「APEX」、トロンボーンとソプラノサックスのユニゾンからソロはPANICHI,LIEBMAN、MILLERと受け継がれる。音色、パワー、テクニック3拍子揃った技量を1曲目から全開のPANICHIに負けじと熱狂的に吹きまくる壮絶なリーブマンのソロも素晴らしい。テーマは一糸乱れずクールに演奏。 オーストラリアのエメラルドグリーンの海をヨットでクルージングしているようなイメージを連想させてくれる2曲目「BARBARA`S SONG」。マルグリューに続くリッチ-・ペリーのテナーソロも自身のリーダー盤よりいいのではないか? 3曲目60年代のBLUENOTEのマッコイ・タイナーの曲をイメージして書いたらしいアルバム表題曲「BLUES FOR McCOY」。 PANICHIの力強いトロンボーンが堪能できるトラックだ。 4曲目はミュートをつけての「CHELSEA BRIDGE」。 バラードをだれることなく最後まで吹ききるのは一流ミュージシャンの証、続くミラーのピアノソロも熟練のうまさが目立つ。 5曲目再びリーブマンが戻って現代モード奏法のお手本のようなスタイルで演奏される。いやいやカッコいい! 6曲目「LISA」3拍子で演奏される美しいスローナンバー。 ラストはデイブ・ストライカーの「FIRST STRIKE」。 確かストライカー自身のファーストアルバム(SOMEDAYの自費出版)でやっていたはず。 最後にDAVE PANICHIは1958年シドニー生まれで1981年にNYへ移りバディー・リッチや秋吉敏子バンドで活躍。 2000年にオーストラリアに戻ってキャンベラの国立大学の教授に就任。教鞭をとるかたわらマイク・ノックのスモールコンボに参加したり自己のグループを結成したりして相変わらず地元の音楽シーンで活躍しているらしい。 録音は1995年 NY CLINTON STUDIO メンバーは上記以外にJAY ANDERSON(B)VICTOR LEWIS(DS) -------- 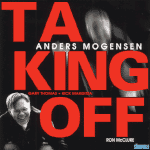 これも倉敷のGREEN HOUSEで1995年の夏に購入した。 リーダーのANDERS MOGENSENの名前は全く知らなかった。 サイドメンは全員が有名。GARY THOMAS(TS)RICK MARGITZA(TS,SS)NIELS LAN DOKY(P)RON McCLURE(B) 全くスタイルの違うテナー奏者がどんな感じで演っているのか? これが購買動機だったと思う。 実質オープニングといってよい2曲目はアップテンポのテナーバトル曲。重爆撃機のようなドスのきいたあの独特なトーンで速射砲のようにソロを展開するトーマスに対し、マーギッツァはブレッカーライクな情熱的でありながらもう一人の自分が見ているかのような巧みにコントロールされた都会的なスタイルでクールにプレイ。 二人の演奏スタイルの対比がよくわかるトラック。 ちなみに二人とも短期間であったがマイルスに雇われたことがある。 3曲目はマーギッツァがソプラノサックスを演奏。ニールス・ラン・ドーキーの抒情的なソロにつづいてマーギッツァーも哀愁度高めのソロを披露。トーマスはお休み。 4曲目表題曲「TAKE OFF」。今度は逆にマーギッツァーが先発ソロ。次第にのぼりつめていくようなマーギッツァーのソロの展開の仕方に対して上空から絨毯爆撃するような重くてハードでどす黒さを感じさせるトーマス。ドラマーにはいい曲を書く人が多いが、MOGENSENもその一人と言っていいだろう。 モンクの「EVIDENCE」もツーテナーで演奏される。この二人音色的には正反対の音色なので、同じ様なフレーズを吹いても全然違うイメージを受ける。柔と硬、技と力、一方は都会的でクールかたや訥弁で刹那的、聴いていて違いがとても面白い。 6曲目「MISSING YOU」この曲でもそう。ソロはマーギッツァー、トーマスの順。 ラストは「朝日の様に爽やかに」で締められる。 2曲目や4曲目なんかは、古くはリーブマン~グロスマン、ブレッカー~ミンツァー、井上淑彦~藤原幹典などのプレイの応酬を連想する。 録音は1994年10月1日 NY SOUND ON SOUND --------  去年の年末、中南米音楽のコメントを見てこれはなんとなく良さそうだなぁと勘で購入。 「ESQUINAS」というアルバム名も中村善郎のセカンドアルバムと同じだし、期待は見事当たって正月休みののんびりした雰囲気にピッタリだった。 アリ・バローゾ1曲、カエターノ・ヴェローゾ2曲、ジョビン1曲のカバー以外は自作曲。作曲家としての才能をとても感じる作品群で、ボサノバ、ブラジル音楽があわせもつサウダージ感覚溢れた曲が抑揚のきいた声でほのぼのとナチュラルに唄われていく。 全部いい曲だが、個人的には2曲目「TUA CHAMA」ジョイスがカバーしそうな4曲目「NO MAR DA CANCAO」が特に気に入っている。 過去の作品を含めて以下のアドレスで試聴もできるので是非アクセスしてみてほしい。 www.betocaletti.com.ar -------- 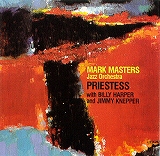 1992年岡山のLPコーナーで買ったCDで、ビリー・ハーパーの名前に惹かれた。演奏曲目もハーパーの「PRIESTESS」コリア「WINDOWS」コルトレーン「NAIMA」「GIANTSTEPS」マッコイ「PASSION FLOWER」と魅力的な曲が並んでいた。 私がジャズを聴ききだした70年代半ば、ビリー・ハーパーはとても人気があった。ブラックセイントやソウルノートからでたリーダー盤、マックス・ローチ・カルテットでの演奏を経てDENON JAZZと契約。矢継ぎ早にアルバムをリリースしてハーパーの人気は最高潮に達する。ジャズ喫茶では一日に何度もアルバムがかけられた。 ライブは合歓ジャズインで観ている。ピアノはアーメン・ドーネリアンだったか?ビリーの日本語のうまさと声のよさ、姿格好の良さを演奏以上に覚えている。 スイングジャーナルでもビリー・ハーパーの一日というグラビアが掲載されたことがあった。朝ジョギングをしてヨガや筋トレで体を鍛え、日本語学校に通うビリーの姿がとらえられていた。 音楽と同じストイックな生活振りが映し出されていてその頃抱いていたジャズミュージシャンのイメージと大分違うなぁと感じた。 そんなビリーの日本での人気はそう長くは続かなかった。 チコ・フリーマンやウィントン・マーサリスが台頭してきて取って代られたのだ。 質実剛健、一直線のビリー・ハーパー本人にすれば時代のニーズに合わせて音楽をつくることなど全く関心がなかっただろうし、いやそういう事を意識さえしていなかったかもしれない。 このアルバムはMARK MASTERS指揮のビッグバンドのソロイストとして、ジミー・ネッパーと一緒に参加したもので、自作曲4曲と「GIANT STEPS」でソロをとっている。 当たり前のことかもしれないが、ビリー・ハーパーの音色、演奏はそのオリジナル曲のなかで最も映える。 不器用で頑固なハーパーの音楽性は結局その閉ざした世界の中で最高のパーフォーマンスを発揮するし、完結すると言ってよいのかもしれない。 実際STEEPLECHASEやオーマガトキ、DIWからリリースされたアルバムでも本質的な音楽性は70年代とほとんど変わっていない。 今は柔軟性を持ち合わせバランス感覚に優れなんでもオールマイティにできるうまいミュージシャンが増えて活躍の場もさすがに多いがビリーの様な世渡りの下手なミュージシャンにもっと演奏の場を提供する動きがあっても良いと思う。 録音は1990年12月4,5日 HOLLYWOOD ------- 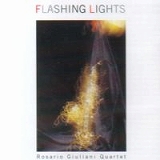 2000年12月岡山「DISC TRANCE」で入手。\690だった。 それまでロザリオのリーダーアルバムや参加作を何枚か聴いていたので即、購入。 ロザリオの場合その魅力は思い切りの良さに尽きると思う。 フルトーンで楽器を鳴らし、目まぐるしいバリエーションのフレーズを次から次へと繰り出していく直情的ともいえるプレイは今のNYの若手奏者にはないもの。 そういう点でマッシモ・ウルバーニのDNAを引き継いでいる現代イタリアン・アルトを代表する一人といえよう。 このCDはエンリコ・ピエラヌンツィ「HINDSIGHT」と他2曲を除いてあとは全てロザリオの作によるものでプレイだけでなく作曲能力も秀でたミュージシャンなのがわかる。 このCDではソプラノサックスも吹いているがロザリオの場合アルトと同じテイストの音色であり、特徴は変わらない。 プレイヤーによっては吹く楽器によって全く違うテイストの音色になる人もいるので、どういう理由でそうなるのか興味がある。 (EX ズート・シムスTS,SS キャノンボール・アダレイAS,SSなど) このCDのインナースリーブにはイタリアのどこかの都市にあるライブハウス(JACKY`S HOUSEと見える)で演奏するカルテットの写真が載っている。 あまり金にはならないが自分達のやりたい音楽を心いくまで演奏することに喜びと充実感を感じている彼らの心情がカットされたひとコマだと感じる。 2001年にはPHILOLOGYより大手のドレフィス・レーベルに移籍、 3枚の作品を発表している。 今後の活躍をますます期待したいプレイヤーの一人である。 録音は1998年7月10日 LAVINIO メンバーはROSARIO GIULLIANI(AS,SS)PIETRO LUSSU(P) JOSEPH LEPORE(B)LORENZO TUCCI(DS) --------  今出張先から帰ってきたところで昼間山口の商店街にある中古屋で買ったこのCDを聴きながら同時にアップさせています。 ELLYN RUCKERはカプリからリーダーアルバムをたくさんリリースしているがこのCDはLEISURE JAZZという知らない会社からのもの。1曲目と2曲目にフェイバレットソングが入っていたのが買った理由。「BEAUTIFUL LOVE」「ISRAEL」。 後はブルー・ミッチェルの「FUNGIMAMA」やボーカルで「SPRING CAN REALLY HANG YOU UP THE MOST」「UP JUMPED SPRING」(F・ハバード)後はエリントンを2曲。 1曲目は情緒深い繊細さを兼ね備えた仕上がり、2曲目は少しハードなタッチで少し演奏が走りすぎかなぁ? 3曲目「TAKE THE COLTRANE」こういう演奏させると本場のクラブでも常日頃揉まれているあちらの連中はこのエリンを含めて本当にうまいねぇ!4曲目「WONDER WHY」3曲目と同じくネイティブの強み、本場ショービズの力は強い。 5曲目もエリントンナンバー「昔はよかったね」 6曲目は弾き語り、7曲目はトリオで唄われる。 ピアノの腕前は歯切れがよく明瞭なタッチで結構力強く弾ききる演奏でスキャットも披露しながら見事なプロフェッショナル振りを見せ付ける。 ラストは楽しい曲「FUNGI MAMMA」で幕を閉じる。 本場の上質なエンターテイメントが収録された一作だと思う。 こういう場にいたら、さぞ美味しい酒が飲めるだろう・・・ 録音は1991年12月7日 NEW ORLEANS MAHOGANY HALL --------  去年12月30日4年ぶりに大阪に帰省して梅田に出た時最後に寄った「ワルティー堂島」のワゴン台にBMCRECORDSのCDが\790で大量に処分されていた。聴いたことの無いレーベルであったが、何枚かチェックしてハンガリーのレーベルなのが直ぐにわかった。 一枚一枚チェックしてみると・・・ このCDジャケの表の片隅にラベンダー色で印字されているDAVID LIEBMANの名前を発見。他に4枚見繕ってレジに持っていった。 このBUDAPEST JAZZ ORCHESTRAはパーソネルをみるとほぼ全員がハンガリー人だと思うのだが、いかんせん知っている名前が一人も見当たらない。 コンダクトはちなみにKORNEL FEKETE-KOVACSという人がやっている。 サックスセクションはフルート、アルトフルート、クラリネット、バスクラなど持ち替えが多彩で、ブラスにはHORN奏者とTUBA奏者がゲスト参加していてサウンド的にはギル・エヴァンスを連想させるところがなきにしもあらず。 デイブ・リーブマンはソロイストとして激情的なソロを例によって展開しているが、知的にコントロールされたそのソロはいつ聴いても納得させる技量と情熱、演奏のダイナミクスを感じさせる。 近年ソプラノの演奏はさらに自由度を増し天空へ飛翔していくかのようなそのパーフォーマンスはスティーブ・レイシ-なき今、ウェイン・ショーターと並ぶソプラノサックス界の双璧をなしていると断言していいだろう。 さてこのオーケストラのサウンドであるが、さすが東欧の国とあってミュージシャンの音楽的レベルが非常に高い。 クラッシック的な部分と伝統的なジャズビッグバンドのサウンドが巧みに交錯し、そこにECM的なサウンドやロックテイストの音が部分的に挿入されるといった具合。リズムの展開が目まぐるしく変わる起承転結がはっきりした組曲風の曲のあってサウンドのバリエーションも多彩な実力あるオーケストラと聴いた。 このBMCというレコード会社リリースしている作品は結構多くて著名なミュージシャンではチャーリー・マリアーノやアーチ-・シェップが参加している作品もあるので下のアドレスでチェックしてみて欲しい。試聴もできるはず。 www/bmcrecords.hu/ --------  10年ほど前になるだろうか六本木WAVEの広告で知って通販で入手したアナログ盤。メンバーが凄い。 JOHNNY GRIFFIN(TS)DADO MORONI(P)LUGI TRUSSARDI(B)ALVIN QUEEN(DS)ISLA EcKINNGER(TR),もうひとつのグループにはMADS VINDING(B)MAKAYA NTSHOKO(DS)ANDY SCHERRER(TS)が参加している。こんなスペシャルなメンバーをバックにスイス人のボーカリストBRIGITTE BADERが唄っているのだ。 選曲も抜群に良い。「GOODBYE PORK PIE HAT」「SOPHISTICATED LADY」「HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON」「BUT BEAUTIFUL」「BEAUTIFUL MOONS AGO」「OUT OF NOWHERE」「YOU`VE CHANGED」「DAY BY DAY」「PRELUDE TO A KISS」に3曲のオリジナル作品の全12曲が収録。 値段が自費出版のためか\3500以上したのを覚えているが、聴いてみたい欲求のほうが強くて買い上げた。 丁寧な歌唱でへたに歌を捏ねくりまわさずストレートに唄うスタイルで好感がもてる。 声質はウィスパー系とか清廉でか細いタイプではなく、かといってパンチが効いた声量のあるタイプでもない中庸の線、口を結構大きく開けて唄っているイメージがするチアフルな唄い方といえばいいだろうか? 決して無理して自分の出来ないことにトライアルするような事はしておらず、等身大の自分をナチュラルに表現しているので、わざとらしさや嫌味がないので、聴き疲れがしない。 アルバムとしてのクオリティーの半分はグリフィンはじめジャズ界の名だたるミュージシャンに任せ、自分の考えるジャズボーカルを素直に歌ったのがこのアルバムの成功のもとだと思う。 結構自身のリーダー盤だから新たなチャレンジだとか日頃慣れていないことに取り組んだり、あれもこれもと色々な歌にトライするアルバムが見受けられるが、たいてい当初の目論見が失敗に終っている事が少なくない。 歌手は無理せず等身大の自分を素直に表現すればそれでいいのだと思う。それが聴衆を感動させる一番の近道なのだから・・・ -------- 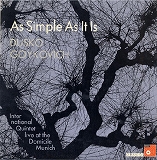 ダスコ・ゴイコビッチを初めて聴いたのはFM放送であった。 渡辺貞夫マイディアライフのスペシャル番組で今までの放送のハイライトでヨーロッパを訪れた時にバークリー以来久々の再会を果たして共演した時の模様がオンエアされたのだ。 ビッグバンドでの演奏だったはずだが、音色の暖かいトランペットを吹くプレイヤーだなぁという印象が残った。 DUSKOのレコードはそれ以来ジャズ喫茶でも聴く機会にめぐられなくDIWからでたアルバムなども見過ごしてしまっていた。 ENJAから久しぶりに出たジミー・ヒースとのCDがきっかけでDUSKO熱が急にでて色々とダスコの入っているアルバムを物色するようになるが、大半は廃盤でしかも高価。 新譜やサイドメン参加作、再発盤は結構手にいれたが、オリジナル盤にはとても手がでなかった。 このアルバムじつは、N山さんにCD-Rにおとしてもらったもの。 3年位前の研究会の時にN山さんのレコード棚に目を通していた時に発見。事情を説明するとCD-Rにしてあげると・・・ N山さんはこのアルバム安く入手した様で今の様に値段が高騰しているのを知らなかったようだ。 肝心のアルバムの出来だが、「ドミシル」でのライブレコーディングという事もあって長尺のソロが聴き応えがある。 現在の様に洗練された柔らかいスタイルのダスコも素晴らしいが、このアルバムが吹き込まれた当時は暖かい音色の中にも情熱や覇気を感じさせ非常に熱気溢れるセッションになっている。 収録は全部で4曲だが、どれもそういう雰囲気が感じられCDだと一気に聴き通してしまう。 録音は1970年1月23日 MUNICH DOMICILE メンバーはDUSKO GOYKOVICH(TP,FLH)FERDINAND POVEL(TS) LARRY VUCKOVICH(P)ISLA ECKINGER(B)CLARENCE BECTON(DS) 当時のヨーロッパジャズの水準の高さをしめす作品のひとつだと思う。 -------- 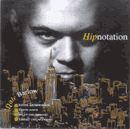 初めて聴いたのは20年以上前にでたCRISSCROSSのシダ-・ウォルトンのカルテット盤だった。 圧倒的な個性には乏しいがフレッシュで将来が期待できる若手テナー奏者が現れたと思った。 それから、リーダー作がでるでもなく、ある時アート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズに参加した事を知る。 それから再びデール・バーロウの名前は見る事が無かった。 1992年の夏、岡山のLPコーナーで新譜チェックしていた時にこの盤を発見。懐かしい名前だったのとサイドメンがEDDIE HENDERSON,KEVIN HAYS,BILLY DRUMMONDと購買意欲をそそる良いメンバーだったので買ったのだと思う。 バーロウとヘンダ-ソン、フロントの二人が頑張っていて曲が進むにつれグイグイ引っ張られていくように、鑑賞にも実がはいる。 ビリー・ドラモンドも全体を鼓舞するような見事なドラミングを展開していてこのセッションの土台を引き締めている。 バーロウは作曲に関しても中々いい曲を書いていてこのアルバムを出来の良いものにしている。 演奏のほうは、ジャズに対して一途というか、情熱を感じられるプレイをしている。が、バーロウ独自の個性というのが少し希薄なところが感じられる。不良性というか、もっと斜にかまえたところがあっても良いと思う。 その点酸いも甘いも経験してきたエディー・ヘンダ-ソンのほうが一枚役者が上と言っていいだろう。 ワンフレーズ、一音で音楽の空気、場を取り仕切る存在感、バーロウも経験を積むことでこの問題はいずれクリアする事だろう。 実際2003年にでたオーストラリアの新作では凄みのあるテナーを聴かせていた。 シダ-・ウォルトンとの再会アルバムも2年くらい前にリリースされたし、オーストラリアに戻ってもコンスタントにリーダーアルバムの吹き込みがあるのは先ほどネットで知ったところ。 これからの活躍をまだまだ期待したい中堅テナー奏者だ。 録音は1990年7月 NY SOUND ON SOUND STUDIO -------  最近、評価が高まってきたベルモンドブラザーズの1994年吹き込み盤で、昨年末、阪神百貨店中古レコード市で\1250で買った。 10年以上前の作品ながらステファン・ベルモンドのその研ぎ澄まされた閃きが感じられるトランペットスタイルは既にほぼ完成されている。テナーのライオネルも60年代のショーター、ヘンダ-ソンのスタイルをよく消化したモーダルなテナーを披露。 ピアノのHENRI FLORENSをはじめリズムセクションの水準も高くサウンド全体が前のめりにグングン押し迫ってくるかのようで、勢いが感じられる。 味わい、情緒には欠けるかもかもしれないが、そんな事は全然問題にならない位、伸び盛りのサウンドを聴かせてくれる。 フランスジャズ界というとルイ・スクラビス、ミッシェル・ポルタル、アンリ・テキシェ、ダニエル・ユメールなど大御所たちの自由度の高いワン&オンリーなジャズのイメージが強いが、ハードバップからベルモンド・クインテットのような正統派モードジャズ路線のグループもあるわけで、依然として層の厚さを感じさせる。 5曲目「A.L.F」でのステファンのテーマ吹奏はとても爽やかな風を感じさせ、晴れ渡った青空をカモメが自由に飛び廻る風景を連想させる。6曲目は日本的情緒を感じさせる曲。 7曲目は新主流派的な構造をもつ曲で昔のウィントン・マーサリスのクインテットを連想させる。 8曲目は唯一のスタンダードナンバー「ダーン・ザット・ドリーム」メロディーを崩さずストレートに吹く姿勢が好ましい。 彼らの基礎がとてもしっかりしたものである事がわかるトラック。 若々しい歌心が感じられて悪くない。 躍動感溢れる「SUNSET IMPRESSIONS」。 ソプラノとトランペットのユニゾンと駆け合いがとても良い。 一押しはこの曲かなぁ・・・後は1曲目と5曲目が個人的にお薦めです。 録音は1994年9月15日 オランダ STUDIO 44 --------  ジェリー・マリガン・カルテットの「木の葉の子守り歌」などで50年代のチェット・ベイカーの演奏をジャズを聴きはじめた頃FM放送なんかで聴いたのだが、その頃はやはりマイルスやフレディー、クリフォードと黒人の50年代ハードバップが一番であまり耳にすっーと入ってこなかったが実際のところだった。 「気まぐれ飛行船」である日チェット・ベイカーの歌がかかった時「その中性的なボーカルに反って男らしい強い意志を感じるとかなんとか」ボーカリストの安田南がコメントしていた時のことを覚えている。その放送でチェットのボーカルに興味をもった。 私はというと、チェットの歌はクリス・コナーなんかをもっと低音にした女性ボーカルのようだなと思った。 しかしその頃はまだインストのジャズを追いかけるのが精一杯でチェットのレコードをはじめて買ったのは、数年後CTIの「SHE WAS GOOD TO ME」が廉価版ででた時だったと思う。 それから研究会でウエストコーストジャズを受け持つことになり、数枚チェットのはいったレコードを買ったはず。 本格的にチェットが好きになったのは、社会に入り酒を飲むようになってから・・・ STEEPLECHACE盤やそのヨーロッパのマイナーレーベルから一頃毎月のようにライブ盤がリリースされていた。 自伝映画も封切られ、それのサウンドトラックもでた。 BRUTUSでチェットの特集号もでたくらい。 80年代になってチェットの人気は日本とヨーロッパでピークに達していた。 そしてあっけない幕切れ。 ホテルの部屋からの転落死。 チェット・ベイカーほどフイルムノワールの雰囲気を漂わせたジャズミュージシャンはいないと思う。 もうこのようなミュージシャンは二度と出てこないように思う。 映画や小説の中のようなことを実際人生の中で経験してきた波乱万丈な一生を送った人。 このレコードは大阪の「MUSIC MAN」で10年以上前格安で手に入れた。レイチェル・グールドのはいった兄弟盤も違う店で同時に入手した。 チェットのレコードの中でも特に愛聴している一枚。 --------  1992年に岡山のLPコーナーで買ったCD。すこし前にDRAGON盤「POEM」を何ヶ月か待って入手したばかりの時だった。 メンバーの豪華さで即、買うことにした。 JOHN SCOFIELD(G)JACK DE JOHNETTE(DS)DAVE LIEBMAN(SS)BILL EVANS(TS)NIELS LAN DOKY(P)ULF WAKENIUS(G)そしてリーダーのLARS DANIELSSONが曲によって様々な編成で演奏したオールスターレコーディング。 去年ラルス・ダニエルソンの新作がACTから久々にリリースされたが、このCDの顔写真とだいぶ人相が変わっていて12年の月日の経過を感じた。この頃はすごく若々しいラルスがジャケに写っている。 1曲目、2曲目はジョンスコのギターがフューチャーされた曲でウネウネした独自のラインはここでも非常に個性的。 3曲目はLARSの特色がよく出た曲調の「FAR NORTH」。 DAVE LIEBMANが北欧の鉛のようなどんよりと厚く垂れ込めた雲の狭間から一筋の太陽の光が差し込むようなきらびやかで物憂げなソロを展開。 4曲目は「枯葉」LIEBMAN,DANIELSSON,DE JOHNETTEのトリオはさすがに変幻自在でありながらプレイに余裕があるというか、スリリングでありながら巧みにコントロールされた印象を受ける。 5,6曲目はULF WAKENIUSのギタープレイが聴ける。 今はスパイス・オブ・ライフから日本盤でCDも出て結構認知されてきたワケニウスだが、この頃はまだ知る人ぞ知る存在だったはず。 7曲目はリーブマンが参加したカルテットによる作品。 ダニエルソンのアルバムでは一番聴きつけているフォーマットだけにやはり一番耳にしっくり来るサウンド。ラストは自身のベースがメロディーを取るピアノトリオの演奏。 録音は1991年1月 NY SOUND ON SOUND STUDIO ラルス・ダニエルソンにしては珍しいコンセプトアルバムやレギュラーグループではないオールスターのセッション盤。 その分ややアルバムとしては焦点がぼけてしまったか? 決して悪い出来ではない。 ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|
||